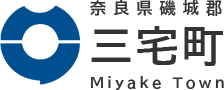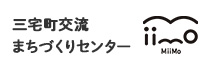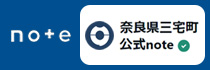本文
後期高齢者医療保険料
保険料を納める方
後期高齢者医療制度では、被保険者となる方全員が、一人ひとり保険料を納めることになります。75歳(一定の障害がある方は65歳)になると、これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった方も、保険料を納める必要があります。
保険料の決まり方
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
奈良県の一人あたりの保険料 (令和4・5年度)
「均等割額」50,500円+「所得割額」総所得金額等-基礎控除(43万円)× 所得割率9.93%=被保険者の保険料(100円未満切り捨て)※ただし上限額は66万円
保険料の軽減
所得の低い方の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が下の表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
均等割額軽減の基準
| 同一世帯内の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 |
|---|---|
|
基礎控除額(43 万円) + 10 万円 × (給与所得者等※ の数 - 1)以下 |
7割軽減 |
|
基礎控除額(43 万円) + 29 万円 × (被保険者数) + 10 万円 × (給与所得者等の数※ - 1)以下 |
5割軽減 |
|
基礎控除額(43 万円) + 53.5 万円×(被保険者数) + 10 万円 × (給与所得者等の数※ - 1)以下 |
2割軽減 |
(※)一定の給与所得がある方または公的年金等の所得がある方
(注)上記の軽減措置を受けるには、税法上の申告義務がない方(障害年金、遺族年金等受給者や所得のない方等)であっても、所得の申告をする必要があります。所得の確認ができている方は申告の必要はありません。
被用者保険の被扶養者だった方
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合等の医療保険)の被扶養者であった方の保険料は、所得割額がかからず、均等割額が資格取得後2年間に限り5割軽減となります。
保険料の納め方
年金から天引きされる場合(特別徴収)
保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の方)から天引きされます。年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方は一時的に普通徴収となります。
※ 年金からの天引きで保険料を納めている方は、申し出により口座振替に変更することもできます。ご希望の方は、役場窓口へ申し出てください。(確実な納付が見込めない方については、認められない場合があります。)
口座振替に変更することにより、社会保険料控除は振替をする口座の名義人に適用され、世帯の税負担が軽くなる場合があります。
納付書・口座振替で納める場合(普通徴収)
年金額が年額18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方等は、納付書や口座振替により個別に市町村に納めます。